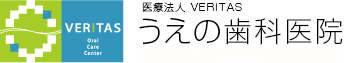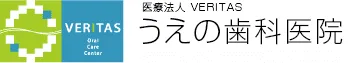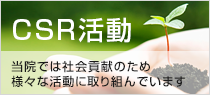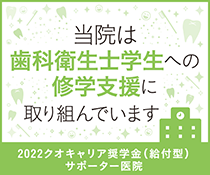2025/10/23【管理栄養士が解説!】秋の味覚があなたの歯を強くする?見逃せない「ビタミンD」の力
皆様こんにちは!
横浜市鶴見区にありますインプラントのヴェリタスインプラントサロン横浜歯周病治療のうえの歯科医院歯科助手・管理栄養士兼トリートメントコーディネーターの高岡です。
涼しくて過ごしやすい季節になってきましたが、皆さんにとって「秋」と言えば何を思い浮かべますか?
紅葉?スポーツ?…それともやっぱり「食欲の秋」ですよね!サンマにキノコにサツマイモ、栗…などなど秋は美味しいものがたくさんあります!
今回は、この豊かな秋の食材たちが、実は皆さんの「歯」にとって、とっても大切な役割を果たしていることをお伝えしていきます。特に、この時期の食材に豊富に含まれるある栄養素、それは…
「ビタミンD」!
今日は、この「ビタミンD」が、私たちの歯の土台である「歯の質」に、どのように影響を与えるのかを解説していきます。
■歯の健康の「縁の下の力持ち」:ビタミンDとは?
まず、ビタミンDと聞くと、「骨のビタミン」というイメージが強いかもしれません。その通り!ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にするためには欠かせない存在です。
実はこのビタミンDは、歯にも影響がある栄養素なのです。
なぜなら、歯も骨と同じように、リン酸カルシウムというミネラルを主成分としているからです。
■太陽の恵みだけじゃない!「秋の食材」は最高のD源
ビタミンDは、日光を浴びることで皮膚でも生成されますが、日照時間が短くなるこれからの季節、そして紫外線を避ける現代生活では、食事からの摂取が非常に重要になってきます。
そして嬉しいことに、旬を迎える秋の食材には、このビタミンDがたっぷりです!
◇ビタミンDが豊富な秋の代表的な食材
◎きのこ類(特に干ししいたけ、きくらげ、舞茸、エリンギ)
• きのこに含まれる「エルゴステロール」は、紫外線(天日干し)を浴びることでビタミンDに変化します。まさに自然のサプリメント!
◎魚介類(サンマ、サケ、イワシ、マグロなど)
・秋の味覚の王様、サンマやサケにも豊富です。
◎卵(黄身)
・年間を通じて摂れる優秀なビタミンD源です。
これらの食材を美味しく食べられる秋は、私たちにとって「天然のビタミンD補給シーズン」というわけですね!
■なぜビタミンDは「歯の質」に欠かせないのか?
ここからが本題です。ビタミンDは、私たちの歯の健康、特に「歯の質」に深く関わる、非常に重要な役割を担っています。
歯質とは、歯の一番硬い部分である「エナメル質」や、その内側の「象牙質」といった、歯の構造そのものを指します。
◇カルシウムとリン酸の「吸収」と「運搬」をサポート!
ビタミンDの最大の役割は、「カルシウムとリン酸の吸収促進」です。
皆さん、歯を強くするために「牛乳を飲まなきゃ!」「小魚を食べなきゃ!」と意識してカルシウムを摂っていますよね。しかし、どんなに頑張ってカルシウムを摂っても、ビタミンDが不足していると、体は食べ物からそのカルシウムを効率よく吸収することができません。
イメージしてください。ビタミンDは、私たちが食べたカルシウムを、腸の壁から体の中へ運び込む「特急列車」のようなもの。この特急列車がないと、カルシウムは途方に暮れて、便と一緒に体外へ排出されてしまうのです。
そして、吸収されたカルシウムとリン酸を、血液に乗せて歯や骨に届ける役割も担っています。つまり、歯の材料(カルシウム)を、材料置き場(歯)に正確に届けるのがビタミンDの仕事なのです。
◇歯の「再石灰化」を促進する!
歯の健康を語る上で欠かせないのが「再石灰化」です。
私たちは食事をするたびに、口の中は酸性に傾き、歯のエナメル質からカルシウムなどのミネラルが溶け出します(これを脱灰と言います)。しかし、唾液の力で口の中が中性に戻ると、溶け出したミネラルが再び歯に戻る現象(再石灰化)が起こり、歯は修復されます。
ビタミンDが十分にあると、血中のカルシウムやリン酸の濃度が適切に保たれるため、この「再石灰化」がスムーズに行われます。
もしビタミンDが不足すると、再石灰化が十分に進まず、脱灰が優位になり、結果として虫歯になりやすい歯質になってしまうのです。
◇歯の成長と形成に不可欠!
特に成長期のお子さんにとって、ビタミンDは極めて重要です。歯の芽(歯胚)が作られ、エナメル質や象牙質が形成される過程で、ビタミンDは細胞の働きを調整し、質の高い歯質を作るのに貢献します。
妊娠中の女性がビタミンDを十分に摂取することも、お腹の中の赤ちゃんの「乳歯」の歯質形成にとても大切だということが、近年の研究で明らかになっています。
■ビタミンD不足が招く、歯の悲鳴
「ちょっとくらい不足しても大丈夫でしょ?」と思わないでください。ビタミンDが慢性的に不足すると、私たちの歯は静かに悲鳴を上げ始めます。
◎虫歯リスクの増加:再石灰化能力の低下、質の悪い歯質の形成により、虫歯になりやすくなります。
◎歯周病のリスク増加:ビタミンDは、免疫機能の調整にも関わっています。不足すると、歯周病の原因菌に対する体の防御力が低下し、炎症が起こりやすくなることが指摘されています。
◎顎骨(あごの骨)の弱体化:歯を支えているあごの骨が弱くなると、歯がグラグラしたり、最悪の場合、歯が抜け落ちたりする原因にもなりかねません。
このように、ビタミンDは「単に歯を強くする」だけでなく、「虫歯と歯周病という二大疾患から歯を守る土台を作る」という、非常に重要な役割を果たしているのです。
■【実践編】秋の食卓で賢くビタミンDを摂るためのコツ
さあ、理屈が分かったところで、具体的な実践方法に移りましょう!
秋の食材を使い、効率よくビタミンDを摂取するための管理栄養士のワンポイントアドバイスです。
◇ 「きのこ」は必ず天日干しを!
生しいたけをザルに広げて30分〜1時間、天日干しにするだけで、ビタミンDの量が劇的にアップします。調理前に一手間加えるだけで、栄養価を大幅にアップできる魔法のテクニックです。市販の「干しきのこ」を活用するのも手軽でおすすめです。
また、冷凍保存することで、きのこに含まれる栄養素の吸収率を高めることもできます。
◇ビタミンDとビタミンKを一緒に摂る!
ビタミンKもまた、カルシウムを骨や歯に取り込むのを助ける重要な栄養素です。ビタミンDがカルシウムの「吸収」と「運搬」を担当するのに対し、ビタミンKは「定着」を担当するとイメージしてください。
ビタミンDが豊富なサンマ、サケなどの魚類
ビタミンK豊富な小松菜、ブロッコリー、海藻類
を上手に組み合わせていきましょう!
例えば「サンマの塩焼き」に「大根おろしと小松菜のおひたし」を添える、など、一緒に食べることを意識しましょう。
◇脂溶性ビタミンDは油と一緒に!
ビタミンDは脂溶性(油に溶けやすい)ビタミンです。油と一緒に摂ることで吸収率が格段にアップします。
・きのこをオリーブオイルやバターで炒める
・サンマやサケを揚げる、あるいはアボカドなどの良質な脂質と一緒に食べる
これも美味しく、賢く栄養を摂るための重要テクニックです!
■まとめ:秋の恵みで、一生ものの丈夫な歯を
いかがでしたでしょうか?
秋が旬の食材に多く含まれる「ビタミンD」が、私たちの歯質に「材料の供給」「修復の促進」「土台の強化」というトリプルアプローチで貢献していることがお分かりいただけたかと思います。
今年の秋は、食卓に並ぶサンマやきのこを見るたびに、「ああ、これが私の歯を強くしてくれているんだな!」と感じていただけたら嬉しいです。
美味しいものを食べて笑顔になる。そして、その美味しいものをいつまでも楽しめる丈夫な歯を持つ。これが、私たちの究極の目標です。
食事の工夫だけでなく、毎日の丁寧な歯磨きと、定期的な歯科検診も忘れずに行ってくださいね。
うえの歯科医院では管理栄養士による栄養指導も行っております。よろしければお問い合わせください。
うえの歯科医院 診療案内